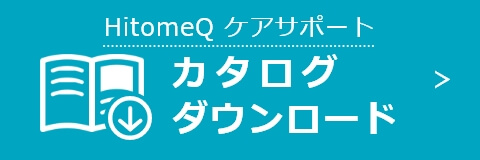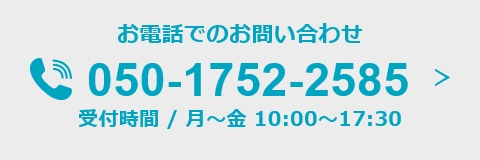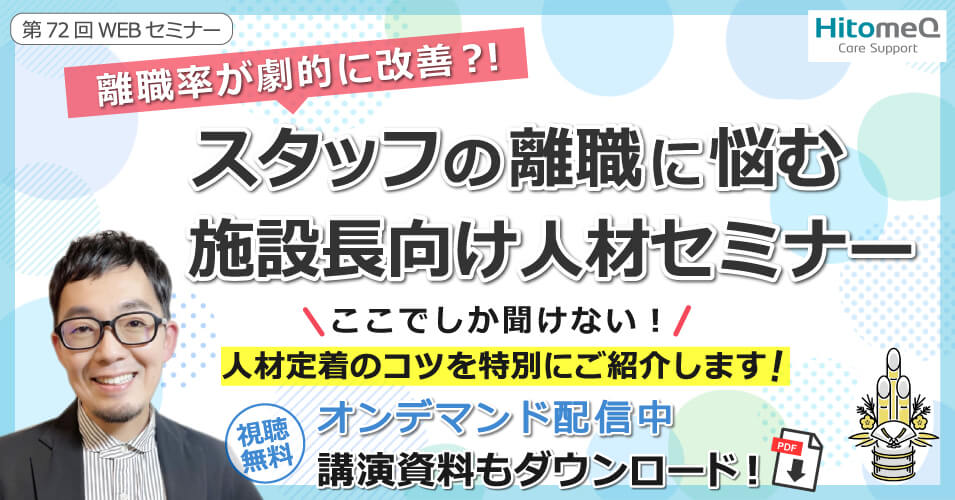常勤換算とは?介護施設が守るべき 職員数の基準と計算方法を解説

常勤換算とは
常勤換算とは、介護施設で働いている人の平均人数のことです。常勤の職員が、何人働いているかについて換算して求めます。介護保険法で人員配置基準が定められているため、正確な数字の把握が必要です。
本記事では、常勤換算の概要や計算方法などを解説します。
常勤換算の基本を知ろう

介護施設では、施設で働いている人の数を正確に把握するために、常勤換算という方法で働き手の数を算出しています。正確な人数を計算する理由は、介護保険法で人員配置基準を満たしていることが必要になるからです。
2022年2月17日に『先進的な特定施設(介護付き有料老人ホーム)の人員配置基準について(これまでの議論の取りまとめ)』というレポートが規制改革推進会議から発表されました。介護施設での働き手の適正な人数について、現在も議論が進められている状況です。
そのため、適正な人数の基本となる常勤換算について、正しく理解しておくことが必要でしょう。まず常勤換算の定義と、この計算方法が重要になる理由を解説します。
常勤換算とは事業所で働く人の平均人数
常勤換算とは事業所で働く人の平均人数です。介護施設は夜勤やパートなど、さまざまな形態の働き方があるため、働く人の正確な人数を算出する際に、通常の常勤の人、1人あたりの仕事量に換算する必要があります。
つまり、常勤換算によって求められた数字は、すべての職員の労働時間を「常勤の職員が何人働いているか」に換算した人数といえるでしょう。
介護職で常勤換算が重要になる理由
介護職で常勤換算が重要になる理由は、介護保険法によって人員配置基準が定められており、その基準を満たしているかどうかを正しく判断する必要があるからです。
人員配置基準は適正な介護を行うためには、一定の数以上の人員の確保が不可欠であることから定められました。人員基準を満たさなかった場合には、指定の取り消しや営業停止などの処分が科されるケースもあります。
常勤換算の計算方法での3つの手順

事業所の管理者は、常勤換算の計算方法を把握することが求められます。事業所トータルでの常勤換算の人数を正しく算出するためには、一人ひとりの勤務時間や、休日の日数を正確に把握することが必要でしょう。手順は大きく分けると、以下の3つです。
- 常勤の人数と週あたりの労働時間を把握
- 非常勤の職員の労働時間を計算
- 常勤と非常勤の平均人数を合算
それぞれについて詳しく解説します。
1.常勤の人数と週あたりの労働時間を把握
常勤の人数を求める数式は以下になります。
| 常勤の職員の人数+(非常勤の職員の労働時間の合計÷常勤の職員に定められた勤務するべき時間)=常勤換算人数 |
ここではSという事業所があると仮定して、具体的な数字をまじえて説明していきましょう。
まずはこの数式の最初の部分にある「常勤の職員の人数」を確認します。S事業所に常勤の社員が12人いるとします。続いて「常勤の職員の勤務すべき時間」の確認も必要です。S事業所では1週間に40時間という勤務時間が定められていると仮定します。
2.非常勤の職員の労働時間を計算
次に非常勤の職員の労働時間を計算して、合計します。S事業所には非常勤の職員がAさん、Bさん、Cさん、Dさんという4人いるとしましょう。Aさんの1週間の合計勤務時間が24時間、Bさんも24時間、Cさんは20時間、Dさんは16時間です。
「24+24+20+16=84」となり、4人合計で84時間という合計労働時間がでました。
3.常勤と非常勤の平均人数を合算
非常勤の合計労働時間である84時間から、常勤職員の1週間の勤務時間である40時間で割ります。84÷40=2.1という数値になるため、非常勤職員の常勤換算の人数は2.1人です。
次に常勤の人数と、非常勤の職員の常勤換算の人数を合計します。S事業所では常勤の社員が12人、非常勤職員の常勤換算の人数は2.1人なので「12 + 2.1=14.1」となり、14.1人という数字が出ました。この14.1人が、S事業所の常勤換算の人数となります。
常勤換算の3つの注意点
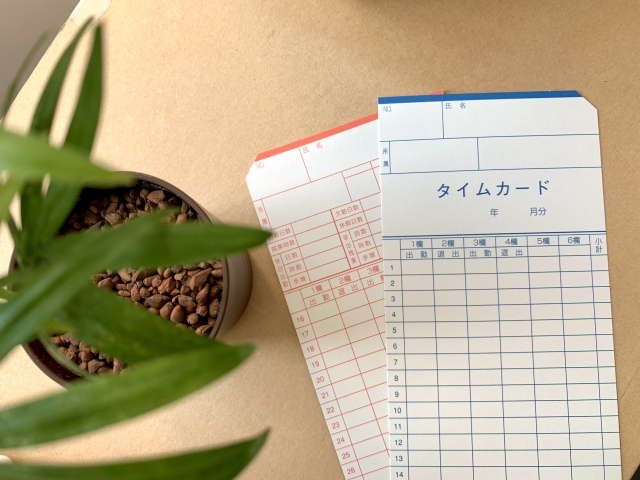
常勤社員の人数は比較的シンプルな数式で求められますが、いくつか注意点があります。
主なものは次の3つです
- 有給休暇と出張の扱い方
- 兼務の扱い方
- 育児休暇の扱い方
常勤換算の正確な数字を出すためには、職員一人ひとりの勤務状況を正確に把握することと、勤務時間への反映の仕方を理解する必要があります。それぞれ詳しく解説しましょう。
1.有給休暇と出張の扱い方
有給休暇と出張の扱い方は、常勤社員と非常勤社員とで異なります。常勤社員の場合は、有給休暇と出張は勤務時間の中に含まれますが、非常勤社員の場合は基本的には含まれない点が大きな違いです。非常勤社員は実際に勤務した時間によって、常勤換算されます。
また、常勤社員でも長期出張や休暇が1ヵ月を超えた場合には、通常の勤務時間の計算から除外されるため注意が必要です。
2.兼務の扱い方
介護職の常勤換算で難しいのが兼務の扱い方です。介護職員は併設している施設で業務を兼務するケースや、系列グループの複数の業種を兼務しているケースが少なくありません。基準は市町村によっても異なります。
同一敷地内で同一の法人が運営していて、並行的に業務を行っても差し支えがないと判断される場合のみ、勤務時間として合計して常勤換算されるルールです。
離れた場所にある事業所や、並行して行うことが困難と考えられる業務は時間を分けて計算します。
3.育児休暇の扱い方
育児休暇や産後休暇は基本的には1ヵ月を超える長期休暇になるため、常勤換算の計算には含まれません。常勤職員が育児休暇の後に短時間勤務を行った場合には、常勤換算の計算では非常勤職員と同様に、実際の労働時間で計算します。
ただし、次に挙げる3つの条件をすべて満たしている場合に限り、常勤に必要とされる1週間の労働時間を30時間として、常勤として計算できます。
- 事業所の就業規則などにおいて、育児による短時間勤務を行っている職員の勤務時間が明確に定められている
- 定められた短時間勤務を行っている職員の勤務時間が週30時間以上である
- 事業所が施設利用者様の対応に問題のない体制を整えている
常勤換算と深い関わりのある人員配置基準とは?

常勤換算が必要になる理由は、人員配置基準があるからです。常勤換算を理解するためには、その前提となる人員配置基準について知ることが必要になります。人員配置基準の要点となるのは以下の4つです。
- 人員配置基準が生まれた背景
- 介護施設の職種別の人員配置基準
- 訪問介護と通所介護の人員配置基準
- 人員配置基準に違反したらどうなる?
それぞれ詳しく解説します。
人員配置基準が生まれた背景
人員配置基準が生まれたのは介護施設において、一定の水準以上の介護を提供できる環境を整えるためです。介護業界では慢性的な人手不足という課題があります。
少ない人数によって、事業所を運営した場合には利用者様へのサービスの質が落ちるだけでなく、職員の負担が大きくなってしまう可能性もあるでしょう。こうした問題を未然に防ぐという目的もあり、人員配置基準が生まれました。
介護施設の職種別の人員配置基準
介護職の人員配置基準の目安は「3対1」の比率です。入居者3人に対して1人の介護職員、もしくは看護職員を配置する必要があると定められています。職種別の人員配置基準は、介護施設の種類によって異なるため、表で詳しく説明しましょう。
有料老人ホームの配置基準
| 職 種 | 配置基準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護職員 | 看護職員と併せて要介護者3人に対して1人以上(常勤換算) | ||||||
| 看護職員 | 入居者30人迄は、1人以上(常勤換算) 入居者50人増すごとに1人追加 |
||||||
| 生活相談員 | 1人以上(常勤換算) | ||||||
| 入居相談員 | 配置基準なし | ||||||
| 機能訓練指導員 | 1人以上(常勤換算) | ||||||
| ケアマネジャー | 1人以上(常勤換算) | ||||||
| 事務員 | 配置基準なし | ||||||
グループホームの配置基準
| 職 種 | 配置基準 | |||
|---|---|---|---|---|
| 介護職員 | グループホーム利用者3人に対して、1人以上の配置 | |||
| 計画作成担当者 | 共同生活の住居ごとに1人以上の配置 1人以上はケアマネジャーの資格を持っていること |
|||
| 管理者 | 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験がある 厚生労働省が規定する管理者研修を修了している |
|||
| 代表者 | 特定の介護施設で認知症・高齢者の介護をしたことがある 保険医療や福祉サービスの事業経営に携わった経験がある 厚生労働省が定めた「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了している |
|||
介護老人福祉施設の配置基準
| 職 種 | 配置基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 入居者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 | |||||
| 介護職員又は看護職員 | 入所者の数が3人又はその端数を増すごとに1人以上 | |||||
| 生活相談員 | 入所者の数が100人又はその端数を増すごとに1人以上 | |||||
| 栄養士 | 1人以上 | |||||
| 機能訓練指導員 | 1人以上 | |||||
| ケアマネジャー | 1人以上(入所者の数が100人又はその端数を増すごとに1人を標準とする) | |||||
介護老人保健施設の配置基準
| 職 種 | 配置基準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 1人以上、常勤1人以上 | ||||||
| 薬剤師 | 実情に応じた数(入居者300人に対し1人を基準) | ||||||
| 介護職員又は看護職員 | 入居者3人に対し1以上、その中で看護は2/7程度 | ||||||
| 支援相談員 | 常勤を1人以上、入居者100人に対し1以上 | ||||||
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 入居者100人に対し1以上 | ||||||
| 栄養士 | 定員100人以上で、1人以上 | ||||||
| ケアマネジャー | 1人以上、入居者100人に対し1以上 | ||||||
人員配置基準に違反したらどうなる?
人員配置基準を下回った場合には、いくつかの段階を経て罰則が科せられます。違反が発覚した場合には、まず指導が行われ監査の対象になります。その後の処分については、違反の程度に応じていくつかの段階があります。
主な処分の内容は以下の4つです。
- 介護事業所の指定の取り消し
- サービス停止
- 新規受け入れ停止
- 介護報酬が減額
介護事業所の指定取り消しとなると、介護事業を5年から10年間行えなくなるという重い罰則になるため、基準を厳守すべく日頃から入念な確認作業が不可欠になります。
ICT活用による配置基準緩和の動向

2021年12月20日に行われた医療・介護ワーキング・グループで、特定施設の事業者から、特定施設の人員配置基準の柔軟化に関する提案があったことを受けて、配置基準を緩和する動きが顕在化してきました。
事業者からの提案内容は、介護ロボットやセンサーなどのICTを利用することによって、「3対1」の人員配置基準よりも少ない職員数で介護サービスの提供を実現できる見通しであるというものです。
介護サービスの質を維持しながら、人員配置基準を下げられる場合、人手不足という課題の解消にもつながります。今後さらに配置基準緩和の動きが活発化することが予想されるでしょう。ここでは、ICT活用による配置基準緩和の動向について詳しく解説します。
夜勤スタッフの配置基準緩和
2021年度の介護報酬改定で、ICTを活用した事業所や施設という条件を満たしている場合には、「夜勤スタッフの配置基準緩和」が行われることになりました。
夜勤の職員がインカムなどのICTを使用している場合、かつ入所者の100%に見守り機器を導入した場合、「夜勤スタッフを1名分多く配置」という条件が「0.6名分多く配置」へと緩和されました。
ICTの活用によって、ケアの質の確保と職員の負担の軽減を実現できるとの判断が、この緩和の根底にあります。
経団連による配置基準緩和の提言
2022年に入ってからの配置基準緩和の大きな動きとして挙げられるのは、1月に日本経済団体連合会(経団連)からの提言です。その内容は「現在の3対1の介護施設の人員配置基準を見直すべきである」というものでした。その背景にはICTの技術の向上があります。
ICTを有効に活用することにより、利用者様にとっての品質を確保しながら、職員の負担軽減と業務時間削減の効果が認められる場合には、改善効果の範囲内で配置を見直すべきであるというのが、経団連の提言の詳細です。
政財界の動向から見ても、ICT導入の環境が着実に整いつつあると考えられます。
ICTを導入して適切な雇用体制を築こう

常勤換算とは介護施設で働いている人の平均人数のことですが、ICTを導入することによって、その人数がより少なくてすむ可能性が高くなってきました。ICTの導入を条件として、人員配置基準が緩和される動きが顕著になってきたことが理由です。
HitomeQ ケアサポートは行動分析センサーとスマートフォンの連携機能、データの分析機能などによって、利用者様へのサービスの質を確保しながら、職員の負担軽減と業務時間の効率化を可能にします。
人員配置基準緩和の議論が進んでいるこのタイミングで、ぜひHitomeQ ケアサポートの導入をご検討ください。