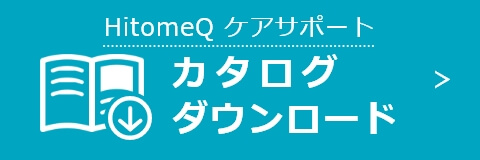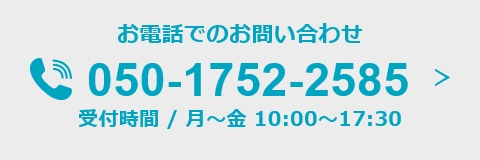住宅型有料老人ホーム メディケア癒やしDX京町台様

右:株式会社SENSTYLE 代表取締役社長 国中様、
左:株式会社SENSTYLE 高齢者行動科学研究所 研究員(医学博士) 樋口様 ※2024年11月時点の情報です。
今回は、株式会社SENSTYLE 代表取締役社長 国中さま、メディケア癒やしDX京町台 現場統括 兼 株式会社SENSTYLE 常勤研究員(医学博士) 樋口さまにインタビューをさせていただきました!
まずは(株)SENSTYLEならびにメディケア癒やしDX京町台さまのご紹介です✒
(株)SENSTYLEさまは熊本を中心に九州で3つの住宅型有料老人ホームを運営されております。
施設さまの特徴としては、平均介護度4.2と医療介護度が非常に高く、スタッフさまが医療従事者(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士)85%以上という高い割合で構成されていることです。
また、全施設100床を越える大型施設となっています。

お話を伺った京町台さまは210床で3施設の中でHitomeQ ケアサポートが最初に導入された施設であり、経営視点でのHitomeQを入れた狙いや、現場での運用面のコツなどを伺ってきました😎
前向きな現場が創るDX成功の形
―― HitomeQの導入決定後、現場の方から不安な声などはあったのでしょうか?
国中さま 基本的には前向きな反応が多かったですね。職員の平均年齢が31歳ということも少しアドバンテージがあるかなという風には思います。ただトップダウンで進めるという組織体制を構築していることと、DXが結果としてスタッフに恩恵があるということを理解してくれている点が1番ですね。
こういったDXを進めていくには、1つの事業を起こすつもりで、経営者が一丸となって取り組んでいく必要があると思います。

―― DXを進めていく上で、「なぜやるのか?」をスタッフさま全体でしっかり理解していることが、立ち上げをスムーズにする秘訣なんですね~!
通知映像をフル活用!転倒リスク7割減の現場改善の秘訣
―― HitomeQ の動画はどのように活用されていますか?
国中さま 通知の動画は必ず見るようにルール化しています。HitomeQの機能を見たときからLIVE映像の確認は必須だと思っていました。訪室の有無や優先順位付けを映像から判断しています。
おかげで転倒は70%くらい減少しましたし、廊下を端から端まで歩く必要がないので、消耗せずに働きやすい環境を作ることができるようになったと思います。

樋口さま 利用者さまのアセスメントを重視して、このような運用も行っています。
利用者さまを「新規入居者様」・「退院直後のご利用者様」・「以前から入居中のご利用者様」の3つのパターンに分類したとき、我々が施設独自で集計したデータによると、「新規入居者様」や「退院後直後のご利用者様」の転倒発生率が3倍ということが分かっております。
原因としては、環境変化による不穏やせん妄などによって転倒リスクが一時的に増加するからであると考えています。

そこで当施設では上記に該当するようなご利用者様には、少なくとも1週間はすべての通知設定をONにするようなオペレーションをとっています。
この対策は単に転倒リスクの高い方への訪室を頻回にすることを目的としているのではなく、LIVE映像によって現在のご利用者の様子を見る機会を増やし、映像からADL評価や行動特性を把握するために行っています。
―― 利用者さまによって、転倒数がこれだけ違うのは驚きでした!
利用者さまの状態をしっかり把握するために積極的に動画を活用いただいているのは嬉しいです✨
「1転倒×1カンファ×24時間以内」 —信頼を築く迅速対応ルールの実践方法
―― HitomeQなどICTを使う上で欠かせない運用ルールはどのように設計されていますか?
国中さま いきなりすべてのスタッフが活用するということはしませんでした。
どういうことかというと、フロアの管理者の数人が徹底的に使いこなすことから始めたんです。
当施設ではHitomeQ ケアサポート以外のICTも活用していますが、どのICTもこのような運用でスタートしています。
よく現場で使われなくなるという話がありますが、これは管理者が使いこなせていないので他のスタッフも使えないということに繋がると思っています。限られた人数の管理者スタッフで使いこなし、上手く運用がハマらない部分や活用が難しい箇所をすべて洗い出して、それに対して1個ずつルールを決めていきます。
全員で使い始めてしまうと後からどんどんルールが増えていって、全員が把握していなかったり、ルーズになってしまう部分があるので、「準備に9割かける」くらいの気持ちをもってスタートしています。
―― 限られたスタッフで徹底的に使いこなしてから全体で使っていくというのは、 事前にルールをしっかり決めておくことで展開してから現場の混乱を防ぐという効果があるんですね!
―― 代表的な運用ルールを教えてください
樋口さま 代表的なもので言うと、「1転倒×1カンファ×24時間以内」でしょうか。
HitomeQ ケアサポートが入る前も「1転倒×1カンファ」というルールはありました。
しかし、状況がわからないのでカンファレンスを開くにもスタッフ自身はもちろんのこと、利用者さまご本人からヒアリングを行ったりと、情報収集に時間がかかり、カンファレンスがなかなか開けなかったんです。

>HitomeQ ケアサポートが導入されてからは、転倒動画を見るだけでよいので、24時間以内というルールが追加され、スピーディーに対応が出来るようになりました。
ご家族さま説明も以前は、転倒のご連絡からカンファレンス後の対策についてお伝えする時間が空いてしまっていましたが、いまは一度に転倒とその対策についてご説明できるので、ご家族からの信頼感も高まると同時にスタッフの精神的な疲労面も軽減できていると感じています。
―― 転倒動画を対策につなげるだけでなく、”24時間以内”という短期間の締切をセットにされているという運用ルール作りは初めてお伺いしました!
ご家族様も転倒の事実と対策が一緒に聞けるのは、安心感が高まりますね✨
現場と利用者をつなぐデータ活用
―― HitomeQのデータはどのように活用されていますか?
樋口さま 使い方としては大きく3つあります。
- ①ケアコールの件数をアセスメントへ活用
アセスメントでは、ケアコール件数で特に夜間帯が多い利用者さまについては日中の行動を増やして、夜間しっかり休めるようにしています。

- ②ケアコールの件数を業務平準化にも活用
スタッフの業務負担がフロアごとによって大きな差が出ないようにデータを活用しています。各フロアの利用者さまの医療度や介護度が平均的になるように、利用者さまにもご協力いただきお部屋のお引越しをしていただいています。
従来は医療度や介護度しか指標がなかったのですが、ケアコールの回数も基準に追加し、動きを均一化することで、スタッフの納得感を醸成しています。 - ③歩行速度を利用者さまの身体機能の評価へ
こちらは最近始めた活用なのですが、転倒が起きた方のデータを改めて見ていたところ、転倒が起きた2週間前頃から変化していたことに気づきました。
今後、「最近危ない気がするな」と思う方を中心にデータを注視していきます。
―― データをこのような形で現場に活用いただいているんですね! ケアコールの件数が利用者さまのアセスメントにも、スタッフさまの業務平準化にも役立っているのは嬉しいですね😊

ケアルーペで見られるデータの一例
管理者層が築くデータ活用の基盤
―― データ活用のコツはありますか?

樋口さま まずは各フロアの管理者・主任がケアルーペを見られる状態にしておくこと。
当施設では管理者は現場半分・管理業務半分という役割を担ってもらっているので、ケアルーペを見て利用者さまの変化を現場に落とすのは適任です。いわゆる中間管理職層に全体のスタッフに先駆けて、何か月もかけて、意義や活用方法をしっかり落としてから全体にリリースをするということが大切だと思います。
中間管理職層が深く理解していることで、その後現場へスピーディーに展開できるんです。
―― HitomeQ ケアサポート立ち上げ時と同様、徹底して管理者層の使いこなしがここでも重要になってくるのですね!
意義を理解した上で納得感を持って進めるというのは大切なことですね。
―― 今後のHitomeQにはどんなことを期待しますか。
国中さま 従来の現場の業務負担削減に加え、スタッフの評価を一緒にできたらいいなと思っています。
介護のクオリティの変化はまだまだ定量化は難しい状態なので、HitomeQ ケアサポートのデータを上手く活用し、スタッフの納得感のある評価をしていきたいです。
―― 現場の業務のDXが進むからこそのICTの次の発展ですね。
ケアそのものをサポートするだけでなく、働きやすい環境づくりもデータをもって支える、そんな姿になっていきたいと思います!
進化するDXの役割 —安心と信頼を支える体制構築へ
―― さいごに、今後の目指す姿を教えてください。
国中さま 医療機関・クリニック・薬局や施設だけでなく在宅とデータ連携することでバイタルを通じて、異変にいち早く気づくアルゴリズムを作りたいです。
これを作ることで行動タスクを考える材料にしたり、延命・安心して長く暮らせるということにつなげたいと思っています。
今後もデータを活用しながら個人の安心安全を担保できるような事業者になりたいですね。
スタッフのさらなる処遇向上はもちろんのこと、ほかができない働き方を目指していきたいと思います。
樋口さま 今後も継続してDXに取り組んでいくことが必要だと考えています。
間接業務を極力なくして、ご利用者さまと関わる直接業務の時間を割けるように、また単に時間を増やすだけでなく、収集されたデータをもとにご利用者さまに適切な医療的な介入やケアを実施できる体制を整えていきたいと思っています。
―― 今や介護もデータをフル活用してどんどん進化していく時代ですね!
私たちも施設さまからお知恵を借りながら、成長し皆様の日々のケアを支えられる存在を目指していきます💪

左から、コニカミノルタ開発担当 岡田、京町台 樋口様、SENSTYLE 国中様、コニカミノルタ営業部長 安井